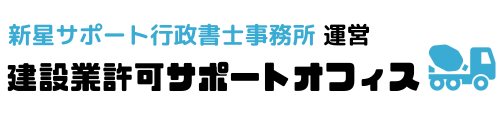【建設業許可】専任技術者とは? 要件は?
建設業許可を申請するとき、資産要件や営業所の要件などを満たす必要があります。その中の一つに専任技術者の設置というものがあります。
ではこの専任技術者とはどのようなものなのでようか? また専任技術者になるにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか?
この記事では、専任技術者について、さらに専任技術者の要件や専任性などについて詳しく解説させていただきます。
専任技術者とは?
まずは専任技術者とはどのようなものか見ていきましょう。
専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する者です。この専任技術者は許可を受ける営業所ごとに設置する必要があます。
また専任技術者になることができるのは、常勤の社員や役員など「専任性」を満たす者になります。さらに専任技術者の要件は建設業法で定められていて、それらを満たすことも必要になります。
では専任技術者の要件とはどのようなものでしょうか? 次に説明します。
専任技術者の要件とは?
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。この記事では、それぞれを分けて説明していきます。
まずは一般建設業の専任技術者の要件を見ていきましょう。
一般建設業の専任技術者の要件
一般建設業の専任技術者の要件は次の通りです。
一般建設業の専任技術者の要件
- 大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種について実務経験を有する者
- 学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
- 申請業種に関して法定の資格免許を有する者(※3年以上の実務経験が必要な場合もある)
上記の3つの要件のいずれかに該当する必要があります。
簡単に説明すると、大卒3年、高卒5年、学歴を問わなければ10年の申請業種について実務経験が必要ということです。ただし大卒や高卒なら「申請に関連する学科」を修めていることも要件です。
また「法定の資格免許」を有している者は実務経験がなくても要件を満たすことになります。(※資格免許の等級などにより実務経験が必要になる場合もあります)
それでは次に①の「申請業種に関連する学科」や③「法定の資格免許」など、いくつか補足で説明していきます。
専任技術者の「申請業種に関連する学科」とは
専任技術者の「申請業務に関連する学科」は、国土交通省令で指定されている学科のことです。(指定学科とも言います)それらの学科を高校や大学で修めた者は、高卒なら5年、大卒なら3年の実務経験があれば専任技術者となることができます。
「申請業務に関連する学科」の詳細は下の「申請業務に関連する学科 一覧」から確認できます。
専任技術者の「法定の資格免許」とは
次に専任技術者の「法定の資格免許」ですが、「申請業務に関連する学科」と同じように指定されてます。それらの指定された資格・免許を取得している者は、原則として実務経験がなくても専任技術者の要件を満たしていることになります。ただし、等級がある資格(検定)等で2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要な場合もあるため、しっかりと指定された資格・免許を確認しなければいけません。
詳細は下の「法定の資格免許 一覧」で確認できます。
専任技術者の実務経験とは
専任技術者の要件のなかに実務経験が必要なものがあります。そして実務経験を有していると認められるには、まず常勤であることが必要です。
また実務経験といえるのは、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験です。これには、現場監督技術者としての経験も含まれますが、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は、実務経験に含まれません。
下に参考資料を貼付しておきますので、より詳しく知りたい方は一読されてください。
特定建設業の専任技術者の要件
特定建設業の専任技術者の要件は次の通りです。
特定建設業の専任技術者の要件
- 一般建設業の専任技術者の要件である①②③のいずれかに該当したうえで、さらに申請業務にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者
- 申請業種に関して法定の資格免許を有する者
- 国土交通大臣が上記①②に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
一般建設業の専任技術者の要件よりも、特定建設業のほうが要件が厳しくなっていることがわかります。また理解しにくい部分もあるので、いくつか補足で説明していきます。
まず①に関してですが、一般建設業の専任技術者の要件を満たしていれば、2年以上の指導監督的実務経験が認められると特定建設業の専任技術者の要件を満たせるということです。
ただし指定建設業(土木、建築、電気、管、舗装、しゅんせつ、造園)については、どれだけ指導監督的実務経験を積んだとしても要件を満たすことはありません。指定建設業は1級資格者が必要とされているからです。
さてここまでで度々出てきている「指導監督的実務経験」とはどういう経験なのでしょうか? 次に説明します。
指導監督的実務経験とは
「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験のことです。
「指導監督的実務経験」と認定されるには、請負金額が4,500万円以上の工事であること以外にも、いくつか条件が定められています。
そして「指導監督的実務経験」は①の要件を満たすうえでとても重要な判断基準となります。ただ非常に細かく条件が定められているため、この記事での説明は割愛させていただきます。
詳しくは下の参考資料で確認してください。
特定建設業の専任技術者の「法定の資格免許」とは
②の「法定の資格免許」は一般建設業の専任技術者の要件の「法定の資格免許 一覧 」と同じ表で確認することができます。
下の「法定の資格免許一覧」で確認してください。
専任技術者の専任性について
ここまで専任技術者の要件について解説してきましが、専任技術者の「専任性」も専任技術者を決めるうえで大切なポイントになるので説明しておきます。
専任技術者の「専任性」とは、その営業所に常勤して、専らその職務に従事していることをいいます。そのため次のような場合は「専任性」があるとはいえません。
専任性が認められないケース
- 住所が営業所から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能な者
- 他に個人営業を行っている者
- 建設業の他社の技術者、常勤役員等、代表取締役など
上記のようなケースでは「専任性」を認められないので、専任技術者となることはできません。
専任技術者を決めるときは、要件を満たしていることと専任性があることをしっかりと確認するようにしましょう。
専任技術者の兼務について
最後に専任技術者の兼務について説明します。先ほども述べたように専任技術者には「専任性」が認められる必要があります。そのため、同一の法人であっても、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
それでは、同一法人の同一営業所では専任技術者の兼務はできるのでしょうか? また同一営業所では専任技術者と常勤役員等(経営業務の管理責任者)の兼務はできるのでしょうか?
同一営業所における専任技術者の兼務はできる?
まず同一営業所で専任技術者の兼務ができるのかについて説明します。
専任技術者は業種ごとに設置します。そのため複数の業種を申請する場合、その業種ごとに専任技術者を決めることになります。
では、複数の業種の要件を1人で満たすものがいる場合は兼務できるのでしょうか?
この場合、同一営業所であれば、その者1人で兼務することができます。ちなみに、同一営業所で同一業種について複数の専任技術者を置くことはできないので気をつけましょう。
同一営業所における専任技術者と常勤役員等の兼務はできる?
次に同一営業所内で専任技術者と常勤役員等の兼務はできるのかについて見ていきます。なお、常勤役員等とは経営業務の管理責任者のことです。
同一営業所であれば、専任技術者と常勤役員等の双方の基準を満たしている者は、両者を一人で兼務することができます。また常勤役員等の他に、専任技術者と常勤役員等を直接に補佐する者や令3条の使用人も兼務することが可能です。
まとめ
専任技術者について、さらに専任技術者の要件などについて解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業で異なること、実務経験と認められる条件や専任性などについてご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外に、専任技術者について疑問などがあれば、管轄の行政庁や建設業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。